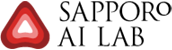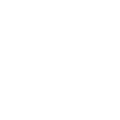本記事は、E資格チャレンジにおいて2024年度まで講座提供を行っていた事業者が作成したカリキュラムを受講し、E資格に合格された方へのインタビューです。
2025年度より、講座の提供事業者・カリキュラム内容は変更となっております。
また、合格者の方の仕事内容や所属先等については、取材当時のものです。
現在の講座内容や募集情報については、こちらのページをご確認ください。
年齢やキャリアに縛られなくていい!

株式会社達人出版会
山根 ゆりえさん(ITエンジニア)
エンジニア向け電子書籍の販売を手がける会社で、取締役を務める山根さん。個人としても長くさまざまなIT業務に携わってきました。しかし、専門領域を絞らずに働いてきたことに「このままでいいのだろうか」と小さな迷いも。そうした中、業界内での盛り上がりを感じていたAIに着目。2024年度の「E資格チャレンジ」を受講し、見事資格取得を果たしました。
「何をしていいかわからなかった状態から、どんな道があるかを示す”地図”を手に入れたような感覚」と話します。
今回は、受講のきっかけから、感じているメリット、学びの工夫、そして資格取得後の環境の変化まで、うかがいました。
今のAIブームは本物だと感じた

–「E資格チャレンジ」を受講したきっかけを教えてください。
私は2023年まで東京都内で働いていましたが、12月に夫の地元である札幌へ移住してきました。仕事はいったんリセットした状態からの再スタートで、「この先どうしよう」と考えていたとき、ふと頭に浮かんだのが「AI」でした。
AIには以前から興味はあったものの、これまで何度かブームが来ては去る印象があり、ずっと横目で見ていたんです。けれど、ここ数年の盛り上がりに「これは本物だ」と感じるようになって。「若い人が中心で、ついていくのが大変そう」と距離を置きつつも「このままでは置いていかれる」と焦りも感じていました。
これまで私は、ITエンジニアとしてアプリケーションからミドルウェア、OSまで幅広く携わってきました。ただ幅広さが強みである反面、専門領域を持たないことに多少の気がかりがあったことも確かでした。札幌という新しい土地で、あらためて「自分の軸」となるスキルを持ちたいと考えたんです。
とはいえ、何から始めればいいかわからず、行動に移せずにいたところ、2024年の8月に札幌AIラボのウェブサイトを偶然見つけて、「札幌って、こんなにAIに力を入れているんだ!」と驚きました。そこから「E資格チャレンジ」の存在を知り、受講を検討することに。数学の行列もあまり覚えておらず、Pythonもほぼさわったことがない状態でしたが、費用面も現実的で、「今逃したら、きっと次はない」と、思い切って申し込みました。
–実際受講してみて、よかったことは何ですか?
受講前は、AIに関して「自分に何ができるのか」「どういうところを深めるべきなのか」が見えていない状態でした。でも、受講を通して全体の構造を把握でき、「この道に進めば、これが得られそう」と想像できるようになりました。
学んでみて関心が深まった分野といえば、たとえば画像解析です。画像は言語への依存が少ないので、世界に通用しやすい点が魅力。自分の手がけたものが国内外に広がる可能性を思うと、モチベーションが高まります。北海道に移住したら関わってみたいと思っていた航空宇宙業界にも応用が効きそうだと考えています。
まだ明確な目的地を見つけたわけではありませんが、「地図」を手に入れた感覚で、いくつものルートが見えてきて、「どこに向かおうかな」とワクワクしています。
早めに完走したからこそ、復習に時間を割けた

–学習は、どのように進めていきましたか?
日々の業務の合間など、空いた時間を無駄にしないように、とにかく「できるときにやる」という姿勢で取り組みました。仕事の時間の融通が利くのが、自分にとって有利な点だったかもしれません。
ただ、当初は受講プログラム全体を「まずは期限内に一通り終わらせなければ」という焦りが先行して。内容の理解より完走を優先してしまった結果、十分に咀嚼しきれないまま進んでしまいました。
「このままではまずい」と思い直したのは、プログラムの最後にある「E資格パッケージ」までたどり着いたときでした。E資格試験本番と同じ形式の問題に取り組む段階です。この演習を有意義なものにするためにも、いったん立ち止まって学び直すことにしました。
まず各単元の講義動画を2倍速で視聴しながら、過去の業務経験と結びつけることでスムーズに理解できる分野と、逆に経験に頼れず理解に苦労する分野を洗い出しました。そして、苦手な部分を重点的に復習した結果、効率よく理解を深めることができたと感じています。問題演習時には、チェックリストを自作して、理解が足りない問題を見える化することで、一問ずつ確実に潰しながら力をつけていきました。
–モチベーション維持やサポート体制について教えてください。
正直、しんどくなる瞬間もありました。でも私は「何かしていないと不安になる」タイプなので、YouTubeで解説動画を見るなどして、少しでも「勉強している自分」でいようとしました。特に、キックオフミーティングで前年度の受講生が紹介してくれた、VTuberによる解説動画は、気楽に楽しみながら見られてとても助かりました。
月1回のオンライン勉強会には、私は都合が合わずリアルタイムでは参加できませんでしたが、録画を配信してくれたのがありがたかったです。積極的に質問してくれる方もいて、「それ、私も気になっていた!」という疑問を代わりに聞いてくれている感覚がありました。講師の方は、質問者の理解度に応じて、丁寧かつ即座に答えてくれるので、皆さんにはぜひ参加をお勧めします。
試験直前期には、他の参加者が「何をやればいいですか?」と率直な質問を投げかけていた際、講師の方が「資格チャレンジを、しっかりやれば大丈夫」とはっきり言ってくださったのも心強かったです。迷いがなくなり、やるべきことに集中できるようになりました。
札幌で出会えたコミュニティが、次の一歩を後押ししてくれた

–山根さんは道外からいらっしゃいましたが、札幌市がこうしたAI人材育成の取り組みを行っていることについて、どんな印象をお持ちですか?
こうした高度なプログラムを、自治体の支援で受けられることは、とてもありがたいことですよね。E資格も個人で受けようとすると、費用的にも心理的にもハードルが高く、「費用や時間をかけて取っても、その分を回収できる保証はない」という不安があります。受講費用や学習時間の確保に対する支援が充実している大企業に勤めている人ならともかく、フリーランスや中小企業のエンジニアにとっては、手を出しづらい資格です。
でも「E資格チャレンジ」のような制度があるおかげで、自分のような立場でもチャレンジできましたし、「札幌市のためにも、ここで終わりじゃなく、これを活かしていこう」と前向きな気持ちになれました。
–資格取得後、具体的に何か活動はされていますか?
E資格を取得したことで、CDLE北海道というAIコミュニティや、札幌AIラボのイベントに参加するようになりました。情報収集の場が増えたことに加え、学んだことをさびつかせずに活かせるチャンスに出会えています。
例えば最近では、CDLE北海道でMCP (Model Context Protocol)という新しい技術をテーマにした開発イベントでハンズオン講師を担当しました。前年(2023年度)にE資格チャレンジを受講して合格した方の協力で実現した機会です。
–最後に、受講を検討している読者の皆さんにメッセージをお願いします。
AIって、若い人のほうが馴染みやすくて、ある程度年齢を重ねた人はちょっと構えてしまうところがあると思います。私もそうでした。でも実際に学んでみると、これまでの技術の延長線上にあるものだと感じました。ベースには、今まで培ってきた知識や経験がちゃんと活きます。
年齢やこれまでのキャリアにとらわれず、少しでも「やってみたい」という気持ちがあるなら、まず一歩踏み出してみてほしいです。その一歩が、新しい景色につながっていくと思います。
取材・文:にの瀬
編集:Sitakke編集部